歯を最小限にしか削らないかぶせもの
かぶせもの(クラウン)は、むし歯治療や根管治療が終わった後、歯の中心部に土台(ファイバーコアなど)を入れて補強し、土台の上から歯の形をした人工物を接着する治療です。
特に、歯髄保存療法や根管治療を行った後は、歯を大きく削ってしまうため歯の強度が下がってしまっています。その時に、つめもの(インレーやコンポジットレジン充填など)を入れてしまうと、歯の強度がかみ合わせの力に耐えられず、歯が割れてしまう可能性が上がってしまうという研究があります。かぶせもの(クラウン)を入れることで、薄くなった歯を補強し、噛めるようにしてかつ歯を割れにくくします。
従来のかぶせもの設計
 従来であれば、かぶせものを入れる際に歯の外周を歯ぐきの下0.5mmまで削りこむことが一般的であり、教科書的であるとされていました。
従来であれば、かぶせものを入れる際に歯の外周を歯ぐきの下0.5mmまで削りこむことが一般的であり、教科書的であるとされていました。
その理由はいくつかありますが、一つはかぶせものの脱離を防ぐために物理的にかぶせている距離をかせぐためであることです。その他、かぶせものと歯との境界部分の段差を歯ぐきの下に入れ、むし歯菌が付きにくくしたり、見た目上有利であったりすることなどでした。
左のイメージ図の青い部分がかぶせものになる部分です。
歯を最小限にしか削らないかぶせものの設計
 従来のかぶせものの設計では、歯を沢山削るため、そもそも歯が薄くなってしまい、歯の強度が下がってしまうという問題があります。また、神経がある歯を沢山削ると、神経へダメージがあり、場合によっては神経を取らないといけ亡くなったりすることもあります。
従来のかぶせものの設計では、歯を沢山削るため、そもそも歯が薄くなってしまい、歯の強度が下がってしまうという問題があります。また、神経がある歯を沢山削ると、神経へダメージがあり、場合によっては神経を取らないといけ亡くなったりすることもあります。
現在では、接着力の高い接着剤の開発により、必ずしも深く削らなくてもかぶせものの脱離を防ぐことが出来ます。また、歯ぐきの下にかぶせものと歯との境界を持ってくることで、歯周病にとっては悪い影響があることもあり、必ずしも良いことばかりではありません。
左のイメージ図ですが、青いかぶせものの部分が減り、健康な歯が増えています。黒い矢印で示している神経の管との距離が明らかに従来の削り方より分厚くなります。歯の強度が上がり、神経が残っている場合は神経へのダメージが減ります。
あとは、見た目の問題をクリアすれば、適用出来ます。セラミックのかぶせものと歯の色との差はどうしても多少出てしまうため、前歯での利用は難しいでしょう。目立ちにくい奥歯が基本となります。

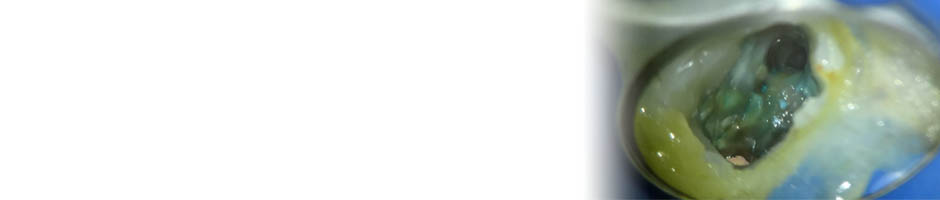
 左の写真の真ん中の歯が最小限に削ったかぶせものをセットした歯です。
左の写真の真ん中の歯が最小限に削ったかぶせものをセットした歯です。 左の写真で青くマークしたところが、かぶせものの部分です。見た目を取るか、健康を取るかはその人それぞれの価値観によるものです。当院の患者さんは、こういった最小限の治療を望む方が多いです。。
左の写真で青くマークしたところが、かぶせものの部分です。見た目を取るか、健康を取るかはその人それぞれの価値観によるものです。当院の患者さんは、こういった最小限の治療を望む方が多いです。。